Soraのフィールドノート#23
- 雅之 三宅
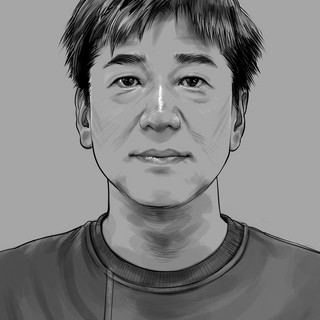
- 2025年10月27日
- 読了時間: 3分
静かに進む畑のアップデート─“続けられる農業”へ|長野県篇
風の匂いが変わるとき、畑の景色もまた変わっていく。長野県では、農業の形が静かに、しかし確かにアップデートされはじめている。
問いは単純だ。どうすれば、ひとりでも、少ない人手でも、畑を続けられるか。
伊那警管区では、生活道路の上空をドローンがすべり、集落と畑を短い直線で結ぶ。

荷は軽やかに、時間は正確に。土の上では自動運転トラクターが等速で進み、作業のムラを削り、体力の消耗を計算に置き換える。

中野市の果樹園では、幹の鼓動を聴くようにセンサーが温湿度や土壌水分を読み取り、AIが生育の“次の一手”を示す。剪定や防除のタイミングが勘から工程へ、経験から共有知へと移り変わる。

豊丘村の田んぼは、朝の見回りがスマホの画面へ。用水の開け閉めは遠隔で、夜の見回りは通知に変わる。水は流れ、時間は戻る。農家の一日から“移動”が抜け落ち、その分“暮らし”が戻ってくる。

新しい道具は、派手さよりも持続に寄与する。機械は疲れず、データは忘れず、ネットワークは待っている。その積み重ねは、離農の坂をゆるやかにし、担い手の入口を広げる。土地勘も、筋力も、長年の勘も──“なくては始められない”条件を少しずつ減らしていく。
もちろん課題は残る。初期費用、電波の谷間、オペレーションの標準化、そして“技術を使いこなす時間”の確保。だが、集落単位で機材を共有し、JAや自治体がデータ連携の土台を整え、学校や地域企業がリスキリングを支えるなら、技術は“持て余す道具”から“地域の基盤”へと育っていくはずだ。

長野の畑は、実はとても実験的だ。標高差がもたらす気象の複雑さ、果樹から米、野菜まで多様な作型、そして集落の結束。ここは“現場の知恵”と“テックの解像度”が交差しやすい地形だ。小さな試みが隣へ渡り、谷を越え、県境を越える。地図には載らない経路で、改善が連鎖していく。

NEOTERRAINは、その連鎖を“つながり”として見つめたい。生産者×テクノロジー×地域金融×教育機関。作る人と支える人、学ぶ場と資金の流れを一本の物語に束ねること。点在する実践を、共有できる“型”にすること。データと経験を往復させ、誰かの失敗が次の誰かの近道になるように。
畑は、季節で動き、人で続く。ひとりでも、少ない人手でも続けられる農業へ。長野から始まる静かな更新が、やがて日本の標準になるかもしれない。そのとき、テクノロジーは“省力化”だけでなく、“暮らしの回復”として語られているだろう。
Youtubeチャンネル「NEOTERRAIN」と連動企画です。動画もチェック!


