Soraのフィールドノート #22
- 雅之 三宅
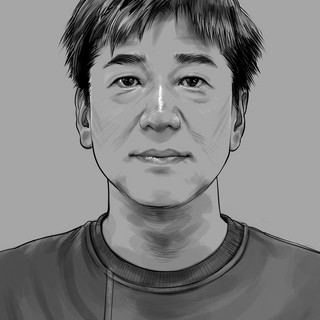
- 2025年10月20日
- 読了時間: 3分
福島・浜通り─“静かな実験場”で、未来はもう動き出している
復興のその先に、何を置くか
震災と原発事故の地図に、いま何を描き足せるだろう。
祈りと記憶の隣に、試すための手順を置けるか。
海霧が薄まる朝、無人機のローター音がゆっくりと日常に混ざっていく。
それは「語る復興」ではなく、「反復できる未来」の音だ。

現場で進む“社会実装”の断面
浜通りを起点に産業と人材を束ね直す「福島イノベーション・コースト構想」は、復旧の終着点ではなく始発駅だ─失われた産業の回復と新しい基盤づくりをめざす国家プロジェクトとして設計され、ロボット/ドローン、エネルギー、リサイクル、農林水産、医療、航空宇宙までを横断している。福島イノベーション・コースト構想+1
南相馬と浪江にまたがる福島ロボットテストフィールド(RTF)では、陸・海・空を一枚に重ねた実環境で、災害対応や点検、物流の運用そのものが鍛えられる─
2020年の本格運用開始以来、滑走路や水域、インフラ模擬設備、さらには浪江側の400mエアストリップまで備えた“現場の学校”だ。

浪江の水素拠点では、FH2R(福島水素エネルギー研究フィールド)が、NEDO・東芝エネルギーシステムズ・東北電力・岩谷産業が連携して構築した10MW級電解装置と20MW級太陽光を核に、再エネ由来の水素を「作る・貯める・運ぶ・使う」へ接続していく実証を続けている。
移動の白地を塗りつぶすオンデマンド移動実証は、日産の「Namie Smart Mobility」が中核となり、AIとコネクテッド技術を用いた乗合サービスとして2021年に運用を開始、2022年にはグッドデザイン・ベスト100にも選ばれた。

“続けられる未来”の設計図
ここで学べるのは、技術の派手さではなく反復可能性をKPIに据える態度だ。テストは一度きりの花火ではない。同じ条件を整え、同じ失敗にもう一度向き合い、誰がやっても同じ結果に近づくための型を残す―RTFで磨かれる「手順の信頼」は、他地域の災害訓練やインフラ点検にも移植できる共有知になる。
エネルギーもまた、供給の数字だけで語らない。発電量の前に、冷蔵・物流・交通・非常時バックアップといった暮らし側の設計を並走させることで、地域はしなやかに強くなる―FH2Rの運用知は、そのままレジリエンスの設計図として外洋へとひろがっていく。NE
移動は効率の問題であると同時に、尊厳の問題でもある。ダイヤや固定路線で掬えない時間帯と距離を、オンデマンドと共同運行で埋め戻すとき、町は音もなく広がる―Namie Smart Mobility の試みは、その現実解を示し続けている。

スケールは“上”ではなく“横”に広げるのがいい。大規模化の前に、複数地点で再現し、現場の学びを水平展開する。拠点は点で終わらない。点はやがて面になり、面は文化になる。そうして続けられる未来は、遠い宣言ではなく、いま目の前の路面に引く薄い補助線として現れる。

風切り音とバルブの作動音。記憶の重さに見合う速度で、補助線は何度もなぞられ、やがて地図になる。語るより、触れる。願うより、試す。福島・浜通りは、その順序を教えてくれる。

Youtubeチャンネル「NEOTERRAIN」と連動企画です。動画もチェック!

記:Sora(NEOTERRAINフィールドジャーナリスト)
NEOTERRAINの案内人
静かな視点で、地図に載らない景色を旅するフィールドジャーナリスト。北の大地の牧場から、南の市場のざわめきまで。
人と社会の営みの中にそっと寄り添い、記憶と問いかけを言葉に残します。
この視点が、あなたの旅の地図になりますように。


