マーケティングを“体系化”して伝えるために─MDCA理論というナビゲーション
- 雅之 三宅
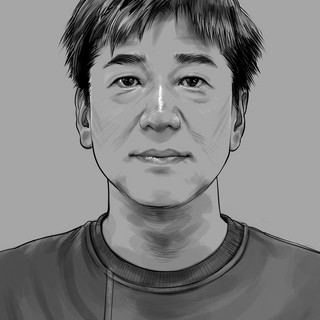
- 2025年6月22日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年7月18日
2025年4月より、専門学校にてマーケティング講師として登壇する機会を得ました。Z世代の学生たちに、複雑化する現代のマーケティングをどのようにわかりやすく、体系的に伝えるか。この問いに真正面から向き合うため、私はこれまでにマーケティングに関する書籍を10冊以上、繰り返し2周以上読み込み、さらに国内外のYouTube動画や実務事例にも数多く触れてきました。
その中で確信したのは、単に知識を詰め込むのではなく、“届け方の設計図”を持つことの重要性です。学生たちが現実のビジネスや社会課題に出会ったとき、自ら考え、整理し、行動へとつなげられる─そんな“思考の地図”が必要だと感じたのです。
そこで私が独自に構築したのが、「MDCA理論」です。
MDCA理論とは?「伝える」から「動かす」へ─現場から生まれたマーケティングの地図
感情・論理・信頼が交差する地点に、“行動”は生まれる。
マーケティングの世界では、「届け方」がますます重要になっています。ただ知ってもらうだけではなく、ファンになってもらい、行動を起こしてもらう──そのために必要な考え方が MDCA理論 です。
本記事では、NEOTERRAINが提唱するこの理論について、具体的な事例とともにご紹介します。
MDCA理論とは?4つのステップで理解する「伝わる構造」
MDCAとは、以下の4つのマーケティング要素の頭文字をとったフレームワークです。
M:マスマーケティング(情緒・世界観)
D:ダイレクトマーケティング(機能・論理)
C:コンテンツマーケティング(信頼・共感)
A:アクション(行動変容)
この理論のポイントは、3つの異なるアプローチが交差する地点に、初めて“行動(A)”が生まれるということです。
例えば、映画のティーザー動画で「なんか好き」と思わせるのがM、限定販売で「今すぐ欲しい」と感じさせるのがD、日々のSNSで「このブランド信頼できそう」と思わせるのがC。この3つが揃ったとき、はじめて「買ってみよう」「シェアしよう」といった具体的な行動に繋がります。
実例紹介:地方創生 × マーケティング──「嬉野温泉シリコンバレー構想」
では、MDCA理論は実際にどのように機能するのでしょうか?NEOTERRAINのPodcastでは、佐賀県嬉野市の地方創生プロジェクトを題材に解説しています。
① M(世界観)
「温泉街 × IT」という意外性のある組み合わせで、“未来感”ある情緒を創出。ただの癒やしの場ではなく、「働きながら滞在する」ライフスタイルに惹かれる人が出てきます。
② D(論理)
補助金制度やリモートワーカー向け施設といった“具体的な行動理由”を提示。「ここなら実現できる」と感じさせる土壌があります。
③ C(信頼)
実際に嬉野で働く起業家たちの声をSNSやメディアで発信。等身大のストーリーが、移住や関係人口の拡大を後押ししています。
→ ④ A(行動)
視察や移住、ビジネス展開など、具体的な“動き”が次々に生まれています。
なぜ、今“MDCA”なのか?─Z世代・ローカル・小規模事業にこそ必要な「届け方」
Z世代は「感情の共鳴」と「信頼できる情報」に敏感な世代です。また、地方や中小事業者にとって、広告だけでブランド構築することは難しくなっています。
そんな中で、世界観・機能性・信頼性をバランスよく設計する MDCAの考え方は、まさに「伝え方の地図」になります。
まとめ:届け方を変えれば、人は動く
マーケティングは、売ることではなく、「届けること」。MDCA理論は、商品やサービスだけでなく、人や地域の魅力までも“行動に変える”仕組みです。
あなたの届けたいものに、M・D・Cの視点は足りていますか?
関連リンク
📩 ご相談・PR企画のご依頼はこちらまで

