地球のおへそ(AIリライト)
- 雅之 三宅
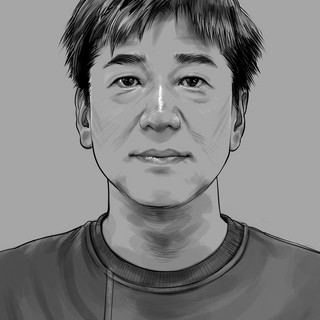
- 2025年4月15日
- 読了時間: 18分
第一章:過去の影
平成22年3月17日。大学の合格通知を握りしめた渋井瞳は、実家の古びた木造家屋の玄関に立っていた。二浪の末、ようやく掴んだ大学への切符。喜びよりも先に、重い安堵が胸に広がった。
「受かったよ。○○大学に行きたい」
父、剛志は、仏壇に手を合わせるのをやめ、振り返った。無表情の奥に、微かな光が宿ったようにも見えた。「…そうか、良かったな」
瞳は、それ以上の言葉を期待していなかった。幼い頃から、家族の心はどこかバラバラだった。特に父に対しては、素直な感情を見せることができなかった。見せたくなかったのかもしれない。感謝の気持ちがないわけではない。ただ、「ありがとう」の一言が、喉の奥で引っかかって出てこない。いつも、そうだ。
大学のキャンパスは、新入生たちの熱気に満ち溢れていた。誰もが新しい人間関係を築こうと、数人のグループで行動を共にしている。そんな喧騒の中、瞳は一人、所在なさげに歩いていた。講義にはきちんと出席しているものの、特別な友達もできず、サークル活動にも興味が湧かない。まるで自分の居場所を探すように、キャンパス内を彷徨っていた。
「サークルでも入ってみようかな」
ふと、そう思った。何か拠り所になるものが欲しかった。部室棟に足を運び、古びた廊下を歩き回る。壁には、色褪せた勧誘の張り紙が何枚も貼られていた。テニス、ラクロス、イベント企画……どれも、今の自分の心には響かない。
そんな中、一枚だけ隅にひっそりと貼られた張り紙が、瞳の目に留まった。
『オーストラリア大陸縦断・三千キロ』
大きな文字でそう書かれた紙は、日付が去年のままになっていた。瞳は、導かれるようにそのサークルの部室を訪ねた。
部室の前には、一人の青年が自転車を組み立てていた。柏木孝之。二年生だと名乗った彼は、明るく気さくな印象だった。意を決して、瞳は声をかけた。
「あの……私、自転車に乗れないんですけど……」
柏木は、手を止めて顔を上げた。「……は?」
「私、自転車に乗れないんですけど、このサークルに入部できますか?」
「はあ。自転車に乗れないの?」
「はい。小さい頃に、練習する機会がなくて」
「珍しいね。大学生になっても自転車に乗れないなんて……」
「でも、自転車に乗れるようになったら、オーストラリアを旅できるんですよね?」
「別に自転車じゃなくても、行けるけど」
「いえ、自転車がいいんです。私、恥ずかしいんです、この年で自転車に乗れないのが」
柏木は、少し考えてから、優しく微笑んだ。「ああ。いいと思うよ。大丈夫だよ」
その時、部室のドアが開き、もう一人の女性が入ってきた。吉崎麻子。三年生で、このサイクリング部の部長だという。
「おはよう」
柏木が軽く挨拶を返した。「ちーす。麻子さん、この子、入部希望ですって。自転車乗れないけど、いいですよね?」
瞳は、緊張しながら頭を下げた。「お願いします」
麻子は、瞳を一瞥し、露骨に嫌な顔をした。「……やだ。面倒くさい。テニスでもやってたら?」
「うわっ、冷たいなあ。別にいいじゃないですか、何でですか? 自転車なんてすぐに乗れるようになりますよ」柏木が慌ててフォローに入った。
「じゃあ、お前が面倒見ろよ」麻子は、そう言い捨てた。
柏木は、困ったように瞳を見た。「いいって」
「ありがとうございます」瞳は、小さな声で言った。
「声が小さい!」麻子が鋭く指摘した。
「すみません」
「イライラすんな」
柏木は、気を取り直して言った。「暇な時、部室おいでよ。色々教えてあげるから。とりあえず、次の合宿は夏休みだから、それまでに自転車と備品を買い揃えてね」
「じゃ、次の授業行くわ」麻子は、そう言って部室を出て行った。
「怖いですね」瞳は、正直な感想を漏らした。
「最初だけ……実は優しいかもね。じゃあ、また明日部室おいで」柏木は、にこやかに言った。
麻子と柏木がいなくなった後も、瞳はしばらく部室に残っていた。壁一面に貼られた写真。それは、自転車で広大な大地を旅する学生たちの、楽しそうな笑顔を切り取ったものばかりだった。
「いいな。楽しそう」
その時、一枚の写真が、瞳の心を強く惹きつけた。それは、柏木が赤茶けた巨大な岩山の上で、大の字になって寝ている写真だった。柏木とオーストラリアの地平線が重なり合い、その向こうから、力強い太陽が昇っている。
「神秘的だな。よし!」
瞳は、決意を胸に部室を後にした。勢いよく閉まったドアには、『パックスサイクリング』という、少し掠れた看板が掛かっていた。
第二章:現在の道
現在。見慣れない田舎道を、三台の自転車が走っていた。先頭は麻子、真ん中が柏木、そして一番後ろに、必死の形相でペダルを漕ぐ瞳。一定のペースを保っているように見えるが、最後尾の瞳と、前の二人との距離は、徐々に開いていた。
「ツライ……休みたいよ」
その時、自転車の車輪が大きくクローズアップされた。次の瞬間、それは回る地球の姿へと変わり、景色は一気にオーストラリアの象徴、エアーズロックへと切り替わった。
タイトルイン。『地球のおへそ』
再び、日本の田舎道。瞳は、汗だくになりながらペダルを踏み続けた。前の二人に追いつこうと、必死に、必死に。しかし、もう足は悲鳴を上げ、思うように動かない。一瞬、意識が遠のき、目を閉じた瞬間、前輪が道路脇の縁石に乗り上げた。バランスを失った瞳は、そのまま横倒しになった。
「ヒトミちゃん!?」柏木が、慌てて駆け寄った。
「気を付けなよ」麻子も、少し遅れて心配そうな表情で声をかけた。
「すみません。大丈夫です」瞳は、よろけながらも自分で起き上がり、路肩に座り込んだ。腕と足には擦り傷ができ、肩を動かすとズキリと痛みが走った。
「麻子さん、少しここで休みましょう。もうすぐで坂道だし」柏木が提案した。
「瞳、走れないの?あまりここでゆっくりできないよ!」麻子は、少し苛立ちを滲ませた。
瞳は、倒れた自転車を起こした。「行きますよ。行きます!」少しむっとした表情を見せた。
「あれ、瞳ちゃんパンクしてるよ」柏木が、後輪を指さした。
「私、本当にだめだ。迷惑ばかりかけてる。もう嫌だ」瞳は、今にも泣き出しそうな声で言った。
麻子は、何か言いかけたが、それを遮るように、柏木が明るい声で言った。「大丈夫、俺得意だから、すぐ直るよ」手際よく工具を取り出し、パンク修理を始めた。
「すみません。ありがとうございます」瞳は、申し訳なさそうに頭を下げた。
「じゃあ、行こう。陽が暮れちゃうよ」麻子が、少し語気を強めて言った。
「はいはい。瞳ちゃん行こう」柏木は、笑顔で瞳を促した。
再び走り出した三人の前には、急な坂道が立ちはだかった。瞳にとって、それは想像を絶するほどの苦しい道のりだった。三人が走る反対車線では、バイクや同じように自転車で走る人々が、互いに手を振り、健闘を讃え合っている。しかし、今の瞳には、そんな余裕は微塵もなかった。
「瞳ちゃん、もう少しで頂上だよ」柏木が、励ますように声をかけた。
「気持ち良い、この景色。最高!」麻子は、息を切らしながらも、周囲の景色を楽しんでいる様子だった。
瞳は、ただ黙って二人の背中を追いかけるのが精一杯で、言葉を発する力も残っていなかった。
「麻子さん、また少し休みませんか?」柏木が、提案した。
「また休憩?」麻子は、露骨に不満そうな表情を浮かべた。
三人は、再び足を止めた。「瞳、走れないの?」
「すみません。遅くて……」
「でも、大分早くなってきたよ」柏木が、フォローした。
「先に行ってもらってもいいですけど、私、迷惑だし……一人で走った方が楽ですよ」瞳は、自嘲気味に言った。
「情けない」麻子が、冷たく言い放った。
「麻子さんは、いいですよね。経験もあるし、楽しんで走っていられるじゃないですか。私は全然楽しくありません」瞳は、抑えていた怒りを露わにした。
「瞳、帰りなよ。このまま坂道下れば楽だよ。近くに駅がある。そのまま帰りな。柏木、行くよ。瞳は一人で走りたいんだって」麻子は、有無を言わせぬ口調で言った。
「でも、僕たちが合わせてあげないといけないんじゃないですか?」柏木が、戸惑いながら言った。
「合わせてあげないと?偉そうに。いいから、行くよ」
瞳は、下を向いたまま、顔を上げることができなかった。柏木は、そんな瞳を一瞥し、諦めたように言った。「わかりました。行きましょうか」
麻子と柏木は、瞳を置いて、先に走り出してしまった。一人残された瞳は、しばらくの間、下を向いたまま、動くことができなかった。その時、瞳の脳裏には、部室での二人の会話が鮮明に蘇ってきた。
第三章:過去の記憶
部室で、瞳は麻子と柏木から、楽しそうにオーストラリアの旅の話を聞いたことがあった。
「この写真、素敵ですね」瞳は、エアーズロックの前で笑顔を見せる二人の写真に目を奪われた。
「ああ、そうなんだ。これね。去年の夏休みに行ったんだ。麻子さんと。楽しかったなあ。色んな人と出会って」柏木は、懐かしそうに目を細めた。
「オージーは皆、大らかで、優しいんだよね」麻子が、相槌を打った。
「途中で出会ったオージーのお兄さんなんて、日本のティーパック、緑茶の。『これプレゼントだよ』って挙げたら、すごく喜んでさあ」
「本当に嬉しそうだったよね」
「それと、あの壮大な自然! カンガルーが俺たちの横を並走するんだよ。あれは感動したなあ」
「何よりも風が強くてね、キツかった。私と柏木が交互に先頭になって、少しでも風をかわして走った。チームワークだよね」
「あとは、星が綺麗だった。隙間がないくらいの星の数で、感動的だったよ」
「あれは……一日の疲れを癒してくれるんだよね。焚き火を焚いてさ、ご飯も美味しく感じるんだ」
柏木は、窓の外の遠い景色を見つめながら言った。「エアーズロック。知ってる? アボリジニ語でウルル。世界で二番目に大きい一枚岩で、地球の中心に位置することから、『地球のおへそ』と呼ばれているんだ」
瞳は、そんな二人の、テンポの良い思い出話に、聞き入っていた。二人の会話は、いつまでも途切れる様子がなかった。
「羨ましいです。いいですよね。共感できる人がいるっていうのは」瞳は、ポツリと呟いた。
第四章:再びの道
現在。瞳は、ゆっくりと立ち上がり、自転車を起こした。そして、再び坂道を登り始めた。心の中で、自分に言い聞かせた。
「絶対この坂道を登りきる。歩いたりしない。私をここまで引っ張ってきてくれたのは、あの二人だよね」
「バカだな、私……私一人じゃ、ここまで来れなかった。麻子さんと柏木さんと、一緒に走りたいな。もう少しで、頂上だ。私も目指すよ、エアーズロック。『地球のおへそ』へ」
過去。多摩川の土手で、自転車に乗れない瞳のために、麻子と柏木が特訓をしてくれていた。
「本当に乗れないんだ? 自転車。へえ〜。天然記念物」麻子は、からかうように言った。
「しょうがないじゃないですか。親は毎日毎日仕事で、遊んでくれた記憶がないんです。皆は、普通お父さんに教わりますよね? 私、そういう思い出がないんです」瞳は、少し寂しそうに言った。
「じゃあ、三人で思い出作っちゃおう。瞳ちゃんが初めて自転車に乗れた日」柏木が、明るく提案した。
「うわ、やばい!」
バランスを崩した瞳は、土手をそのまま下へと突っ走って行った。二人の心配をよそに、必死にハンドルを握りしめていた。
現在。瞳は、懸命にペダルを漕ぎ続け、ようやく坂の頂上に辿り着いた。そこには、麻子と柏木が、大の字になってアスファルトの上に寝そべっていた。
「瞳ちゃん、待ってたよ。ここ、気持ち良いよ。休みなよ」柏木は、優しい笑顔で言った。
「気持ちイイな〜。この景色と空気。諦めたら、もうそれでおしまい。その先に楽しみや感動はないんだよ」麻子は、空を見上げながら言った。
瞳は、そのまま倒れ込むように横になった。同じように仰向けになり、目の前に広がる空は、どこまでも青く、気持ちが良かった。日陰で覆われたアスファルトは、ひんやりと冷たく感じ、通り抜ける風が心地よかった。
「ごめんなさい。さっきは……」瞳は、素直に謝った。
「さ、行こう。陽が暮れちゃう」麻子は、立ち上がりながら言った。
「はい、行きます。行きましょう!」瞳も、力強く頷いた。
「……」柏木は、二人を見守るように微笑んでいた。
「あんたは、仲間だよ」麻子が、不意に言った。
「え?」瞳は、驚いて麻子の顔を見た。麻子の表情は、どこか優しかった。
第五章:旅の途中
田舎道を走る途中、三人は小さな商店に立ち寄った。喉を潤すためにジュースを買って飲んでいると、お店のお婆ちゃんが、にこやかに話しかけてきた。
「あんたら、どこから来たんだい?」
「東京ですよ」柏木が答えた。
「あらまあ、東京からこの自転車で来たんかい。ほれ、うちで、お茶でも飲んでいきな」
「え、いいんですか。甘えちゃって」瞳は、遠慮がちに言った。
「いいよ、いいよ。休んでいきな」
「いえ、大丈夫です。急ぎますから……」麻子が、申し訳なさそうに断った。
「ごめんね、お婆ちゃん。一度休むと、動けなくなっちゃうからさ」柏木も続いた。
「……」瞳は、二人のやり取りを静かに聞いていた。
「そうかい、ちょっと待ってな」お婆ちゃんは、そう言うと、奥からジュースとお菓子を持ってきてくれた。
「ありがとうございます。遠慮なく頂きます」麻子は、深々と頭を下げた。
お婆ちゃんは、瞳をじっと見つめた。「あんたは、このお二方に比べると、弱そうやから、心配するよ。気をつけなね。私の孫も、海外旅行ばっかりで、心配でしょうがない……気をつけなね」
お婆ちゃんの温かい言葉に、瞳の胸は熱くなった。三人は、今夜の宿泊先であるキャンプ場を目指し、再び走り出した。瞳は、麻子と柏木よりも、さらに遠い先を見つめていた。
「私、行ける。エアーズロックへ」
胸の奥で、強い決意が湧き上がってきた。
キャンプ場の入り口に到着した。「到着。お疲れ」麻子が、軽く言った。
「やったー。ご飯楽しみだな」瞳は、珍しく素直な喜びを露わにした。
「まだまだこれから、テントの組み立てや夕飯の準備があるからね」柏木は、自転車のメーターを見た。「今日は走行距離八十七キロか。瞳ちゃん、お尻痛いでしょう?」
「はい。ちょっと、やばいかも……です」
「慣れるよ。その内、皮が厚くなるから」麻子は、あっけらかんと言った。
「……」瞳は、苦笑いを浮かべた。
キャンプ場の受付には、愛想の良いおじさんがいた。三人が横一列に並ぶと、おじさんは顔をしかめて言った。「自転車か? 東京から? 若いなあ。しかし、あんたら臭いなあ」
「青春の汗ですよ! スポーツの汗!」柏木が、胸を張って言った。
「臭くありません! これが本当の人間臭さ、シズルです!」瞳も、負けじと言い返した。
麻子は、瞳の意外な反応に、小さく笑った。「はは、お姉ちゃん、元気良いなあ。うちの温泉は良いでぇ。入っていきな」
「あざーす」麻子は、軽く頭を下げた。
テントエリアでは、麻子と柏木が手際よくテントを張り始めた。瞳は、まだ慣れない手つきで、二人の手伝いをした。麻子と瞳は同じテント、柏木は一人用の小さなテントだ。
「たまには、三人で寝ませんか?」柏木が、冗談めかして言った。
「いやだ」麻子は、即答した。
「いいですよ、私は……柏木さんなら安心だし」瞳は、少し照れながら言った。
「あほか」麻子は、きっぱりと言い切った。
「オーストラリアの時もそうだったじゃないですか。一ヶ月も一緒にいたのに、全く……麻子さんとも、これが最後の合宿なのに……」柏木は、少し寂しそうに呟いた。
「えー、最後くらい、仲良く寝ましょうよ」瞳が、遠慮がちに提案した。
「しつこい!」麻子は、語気を強めた。「はい、ご飯の準備。瞳はお米係り。柏木は野菜を切って。私は、先にお風呂に入ってくる」
第六章:夕食の支度
炊事場では、柏木と瞳の二人が、夕食の準備に取り掛かっていた。
「瞳ちゃん、本当に一人でオーストラリアに行くの?」柏木が、何気ない様子で尋ねた。
「何でですか?」瞳は、手を動かしながら聞き返した。
「女の子一人じゃ、不安じゃない? 親も心配するでしょう。許してくれるの?」
「あー、関係ないです。親は……好きじゃないんです。親の話はしないでください。親もきっと、興味がないんだと思います」瞳の声は、わずかに震えていた。
「そんなことないよ。心配しない親なんていないよ」柏木は、優しく諭すように言った。
「私の家は、違うんです」瞳は、そう言い切った。
「……」柏木は、それ以上何も言えなかった。
「あ、すみません」瞳は、気まずそうに謝った。
テントエリアに戻ると、麻子が一人、ビールを飲みながら火の準備をしていた。「お帰り。この鮎、受付のおじさんがくれたよ」
「いいねえ。これだから、キャンプはやめられないんだ」柏木は、嬉しそうに鮎を受け取った。
瞳は、鍋に入った米を火の上に置いた。「上手く炊けますように。焦げませんように」と、小さな声で呟いた。
しばらくして、「そろそろ白いご飯できたかな」と、柏木が待ちきれない様子で尋ねた。
「いきまーす。ほら」瞳は、炊き上がったばかりの鍋を差し出した。
「うわ、ばっちりじゃん。真っ白だよ」麻子が、目を丸くして言った。
「うまそー」柏木も、顔を綻ばせた。
三人は、「いただきます」と手を合わせ、温かい夕食を囲んだ。
第七章:語らいの夜
夕食後、三人はテントの前で、焚き火を囲みながらビールを飲んでいた。
「二人って、本当に仲良いんですね」瞳が、ふと呟いた。
「最初は、喧嘩ばかりだったよ。麻子さん、覚えてますか? 千葉の合宿で大げんか……」柏木は、遠い目をしながら言った。
「最悪……」麻子は、顔をしかめた。
過去。千葉の海岸線を、麻子と柏木、そして他の部員三人が走っていた。リーダーとして、麻子は懸命に先頭を走り、チームを引っ張っていた。しかし、他の部員たちは、先頭を走る麻子のスピードが遅すぎると感じ始めていた。
「すいません。麻子さん、先行きます」一人の部員がそう言うと、他の二人もそれに続き、一気に麻子たちを追い抜いて先へ走って行った。
後から、ようやく追いついた麻子と柏木。麻子は、怒りを露わにした。「あんたたち、ふざけんじゃないわよ! 合宿の意味がないでしょう! 勝手に走りたければ、一人で走れ!」
「麻子さんが遅いんですよ。合わせてられねーよ。何が団体行動だ。古くせっ」別の部員が、吐き捨てるように言った。「行こーぜ。俺たちだけで……柏木はどうする?」
「お前たち、少し勝手すぎるだろうが。みんなで走ろうぜ。それぞれペースってもんがあるんだ。合わせることも大切じゃないのかよ。それに、スピードだけじゃない。楽しむことも大切だろ」柏木は、必死に説得しようとした。
「かったるいことばかり言ってんなよ」部員は、うんざりした表情で言った。
「ごめん、私、着いて行くから、先走っていいよ」麻子は、悔しさを押し殺して言った。
「分かりました。追いてきてください」部員たちは、そう言うと、再び走り出した。
しかし、麻子は、途中でどうしてもついていくことができなかった。目的地には、他の部員たちより大分遅れて到着した。麻子は、何も言うことができなかった。他の部員たちは、麻子の言うことに耳を傾けようとはしなかった。
現在。「あの夜、テントの中でずっと泣いてたもんな、麻子さん」柏木は、静かに言った。
「あれ以来、この部は二人だけ……」麻子の声は、どこか寂しげだった。
「あっ、柏木さん、ごめんね。私、遅いから。イライラするでしょう?」瞳は、申し訳なさそうに言った。
「そんなことないよ。ちょうど良い。瞳ちゃんのペースだと、景色もよく見えるし。麻子さんの可愛いお尻を見ながら走るのも、悪くない」柏木は、冗談めかして笑った。
「ただの自転車好きの女好きだろ」麻子は、呆れたように言った。
「オーストラリアでも、ずっと二人だったんですよね」瞳は、二人の過去に興味津々の様子だった。
「早く風呂に入っておいでよ」麻子は、瞳に促した。
「いえ、今日は入りません。この汗臭いままがいいんです。好きなんです、この臭いが」瞳は、少し変わったことを言って笑った。
「風呂入りまーす」柏木は、そう言って立ち上がった。
第八章:夜の語らい
夜も更け、それぞれのテントに戻った。瞳は、隣のテントにいる麻子に、そっと声をかけた。「麻子さん、まだ起きてますか?」
「何?」麻子の低い声が返ってきた。
「麻子さんは、自分のこと、好きですか?」瞳は、少し躊躇いながら尋ねた。
「……」麻子は、しばらく沈黙した。
「私は、自分が嫌いです。親とも上手くいってないし、親友と呼べる友達もいない。自分に自信もないし……二年もかけて大学に入ったのに、つまらなくて、辞めようと思ってたんです。でも、そんな時、このサイクリング部の存在を知って、麻子さんや柏木さんと出会えました」瞳は、静かに自分の内を語り始めた。
「……」麻子は、相槌も打たずに聞いていた。
「目標もできました。エアーズロックに行きます。地球のおへそを目指して。手紙書きますね。写真も送ります。エアーズロックから」瞳の声には、強い決意が宿っていた。
しばらくの沈黙の後、麻子は、低い声で語り始めた。「瞳、さっき臭いって言ったよね。空港には、その国独特の臭いがあるんだ。モロッコ、モスクワ、スペイン、オーストラリア……それぞれの臭いがある。空港には、ドラマがあるんだ。私、好きなんだ、空港の臭いが……お父さんに電話してあげなよ。頂上から、おへその上から」
「はい。そうします。たぶん」瞳は、小さく答えた。
隣の柏木のテントからは、二人の静かな会話が聞こえてきていた。
第九章:別れと旅立ち
翌朝、三人は出発の準備を終え、最終目的地である駅へと向かった。
「ラストラン。行こう、目的地へ」麻子が、力強く言い放った。
田舎の駅前に、三台の自転車が並んで到着した。「お疲れ〜」麻子が、労いの言葉をかけた。
「お疲れ様です」柏木も、笑顔で応じた。
「ありがとうございました」瞳は、深々と頭を下げた。
三人は、それぞれ握手を交わし、最後に記念撮影をして、今回の合宿を終えた。
●一年後
空港の出発ロビー。輪行バッグをカートに乗せた瞳の姿があった。麻子と柏木は、オーストラリアへ旅立つ瞳を見送りに来ていた。
「瞳、気をつけて……これ、私の友達の連絡先。何か困ったことがあったら、電話してみて。きっと協力してくれるから」麻子は、一枚の紙を瞳に手渡した。
「瞳ちゃん、大丈夫? 気をつけて」柏木は、心配そうな表情で言った。
「本当にありがとうございます。生きて帰ってきます。そこまで大げさじゃなし」瞳は、笑顔で答えた。
「大丈夫だよ。日本人、たくさんいるから」柏木は、冗談めかして言った。
「じゃ!」麻子は、 коротко 言って手を振った。
「アデレードからエアーズロックまで、約三千キロ。きっと楽しい旅になるよ。頑張って」柏木は、瞳の背中に向かってエールを送った。
麻子と柏木と別れた瞳は、一人になると、ふと時計を見た。出発予定時刻まで、まだ時間がある。広いロビーの中で一人佇んでいると、一瞬、孤独と不安が押し寄せてきた。父親に電話しようか、迷った。
(オフナレ)お父さん、怖いよ、私、すごく不安なんだ。一人でオーストラリア、行けるかな……
その時、日本の実家では、瞳の父親、剛志の携帯電話が鳴っていた。
第十章:繋がる想い
瞳の実家のリビング。剛志は、鳴り響く携帯電話を手にした。「もしもし……」
「お父さん? 私、瞳。エアーズロックに着いたよ。ごめんね。心配したよね?」遠く離れたオーストラリアから、娘の声が聞こえてきた。
剛志は、言葉を失い、しばらく沈黙した。「……」
「ありがとう、お父さん。今まで、ちゃんと話してあげられなくて、ごめんね」瞳は、精一杯の感謝の気持ちを込めて言った。
「疲れたろ? ゆっくり休みなさい。実家で待ってるからな。早く、帰ってきなさい」剛志の声は、少し震えていた。



